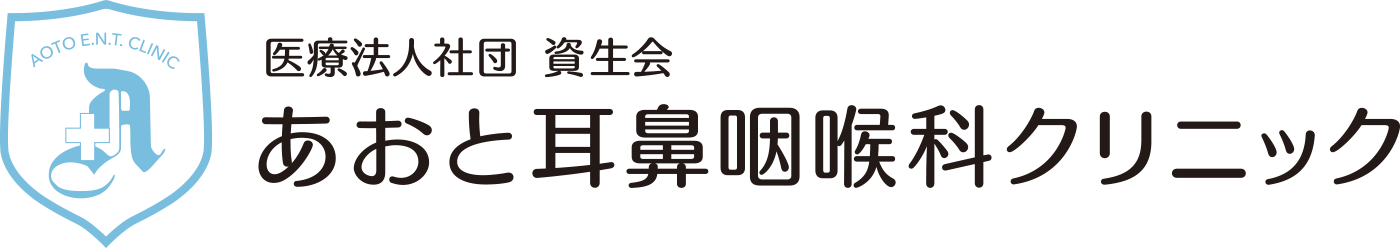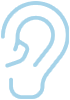診療メニューmenu
突発性難聴
-
ある日突然、聴こえが悪くなる病気で原因は不明です。耳鳴りを伴うことも多く、強いめまいとともに発症する場合があります。内耳の、音を感じる有毛細胞の障害で起こると考えられています。可能な限り早く診断をして治療を始めると聴力が回復することもありますが、発症してから長期間放置していると、治療しても難聴や耳鳴りが残ってしまいます。メニエール病、外リンパ瘻など、似たような病気がありますので、注意が必要です。難聴が高度の場合は入院が必要となり、ステロイドホルモン剤の点滴、ビタミンB製剤、循環改善剤などで治療しますが、一番大切なのは、とにかく早く耳鼻咽喉科を受診することです。
急性中耳炎
-
大部分がかぜに引き続いて起こるもので、耳管を通って細菌等が中耳に入り炎症を起こします。ウイルスが原因のこともありますが、大部分は細菌感染によるものです。症状は耳痛、発熱、かぜ症状などで、中耳腔に膿が多く貯まりますと鼓膜を切開して膿を出す(鼓膜切開術)ことが必要となることがありますが、切開する前に自然に鼓膜に穿孔ができて膿が出てくることもあります。細菌が原因の場合でも、程度が軽い場合は抗生物質は必要ないこともあります。しかし、中等度から重度になりますと適切な種類の抗生物質を、最低限必要な期間内服することが重要です。この治療が不十分ですと、滲出性中耳炎や慢性(化膿性)中耳炎になる原因となります。それを避けるために、耳鼻咽喉科を受診することが重要です。また、鼻やのどの治療を同時に行います。
花粉症
-
50年程前より毎年、春先になるとスギ花粉、スギに続いてヒノキ花粉が飛散して、多くの人がアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎などを引き起こし、日常生活への影響の大きさから社会問題にまでなってきています。スギ花粉症の対策としては、花粉の本格飛散が開始する数日前(東京では2月の上旬頃)から、抗アレルギー剤と呼ばれる第2世代抗ヒスタミン剤やロイコトリエン拮抗剤などを服用し、ステロイド製剤の点鼻薬もこの時期から使用を開始することもあります。この治療を飛散が終了する5月の連休頃まで続けます。これを基本として、症状が重くなる花粉の最盛期にはステロイド製剤の点鼻薬や鼻づまりを軽減する血管収斂剤の点鼻薬を併用します。これらの治療でつらいスギ、ヒノキ花粉の季節もとても快適に過ごすことができます。またスギ、ヒノキの他には5月~6月頃のイネ科の植物、8月下旬~9月頃のブタクサなどの花粉も原因となります。
アレルギー性鼻炎
-
アレルゲンと呼ばれる原因物質が鼻の中の粘膜に触れるとアレルギー反応が起こり、鼻水、くしゃみ、鼻づまりが出てきます。アレルゲンとしては、ダニ、ハウスダスト、カビなどの他にスギなどの花粉があります。治療は、アレルゲンを遠ざけることが大事ですが、現在、多くの抗アレルギー剤が出ており、これらの抗アレルギー剤(第2世代抗ヒスタミン剤やロイコトリエン拮抗薬)の内服を基本として、ステロイド製剤の点鼻薬や鼻づまりを軽減する血管収れん剤の点鼻薬を併用したりします。他には、舌下免疫療法も行われることがあります。
急性扁桃炎
-
のどには扁桃がいくつかありますが、とくにその中でも口蓋扁桃が細菌感染によって炎症を起こし、腫れた状態です。強いのどの痛み、38℃以上の発熱や悪寒などの症状で、かぜとは違い、抗生物質が必要となります。原因となる細菌が溶連菌の場合は、ときに腎炎や心内膜炎を起こすことがあるので注意が必要です。ただ、EBウイルスの感染で起こる、伝染性単核球症という病気の一症状であることもありますので、この場合は抗生物質の使用は逆効果になります。
花粉症
-
50年程前より毎年、春先になるとスギ花粉、スギに続いてヒノキ花粉が飛散して、多くの人がアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎などを引き起こし、日常生活への影響の大きさから社会問題にまでなってきています。スギ花粉症の対策としては、花粉の本格飛散が開始する数日前(東京では2月の上旬頃)から、抗アレルギー剤と呼ばれる第2世代抗ヒスタミン剤やロイコトリエン拮抗剤などを服用し、ステロイド製剤の点鼻薬もこの時期から使用を開始することもあります。この治療を飛散が終了する5月の連休頃まで続けます。これを基本として、症状が重くなる花粉の最盛期にはステロイド製剤の点鼻薬や鼻づまりを軽減する血管収斂剤の点鼻薬を併用します。これらの治療でつらいスギ、ヒノキ花粉の季節もとても快適に過ごすことができます。またスギ、ヒノキの他には5月~6月頃のイネ科の植物、8月下旬~9月頃のブタクサなどの花粉も原因となります。
手足口病
-
ウイルス感染による夏かぜで、のどの痛みと発熱を認めてのどや口の中に水疱ができるのと同時に、手と足にも水疱ができます。のどにできる水疱の位置がヘルパンギーナと少し違うため、見るとだいたい区別できます。対症療法で治療します。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
-
ムンプスウイルスの感染によって、耳の下にある耳下腺という唾液を作るところが腫れる病気です。片側あるいは両側の耳下腺が腫れて痛みが強く、熱も出ます。顎下腺が腫れることもあります。まれに内耳にも障害が及んで片側の難聴を起こすことがありますが、これは感音難聴という、治療をしても治らない難聴ですので注意が必要です。一度かかるとその後はかからない(終生免疫)のですが、まれに繰り返し感染することがあります。予防接種が行われています。治療は症状を軽くする対症療法しかありませんが、約1週間から10日程でよくなります。
 診療時間 診療時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | |||||||
| 15:00~18:30 |
アクセスaccess
〒125-0062
葛飾区青戸3-37-6 holy.comビル3階
京成線青砥駅から徒歩1分
キッズスペース完備
〒125-0062
葛飾区青戸3-37-6 holy.comビル3階